頭の中がなんだかモヤモヤして、考えがまとまらない。
何かを変えたいと漠然と思うけど、忙しくて後回しにしてしまっている。
最近、頭をフル回転させているという感覚がない。
放っておいても何とかなりそうだけど、不安な気持ち。ありますよね。
本書で紹介されているノート活用術、そんな時に前に進むキッカケになるかもしれません。
- 頭を整理したい
- 思考力をつけたい
- 自己分析のやり方に悩んでいる
- 頭の中でモヤモヤしている目標を具体化したい
- 書くことが嫌いではない
- 筆記具やノートが好きだけど、うまく使いこなせない
- 既に目標の立て方が確立している
- ノートをキレイにまとめる方法を探している
- 書くことが嫌い
- 書籍の記載の一つ一つに科学的エビデンスを求める方
著者について

- 安田修氏
- 1976年生まれ
- 会社員経験(日本生命)を経て、2015年3月に起業
- (株)シナジーブレイン代表取締役
著者のブログのこの記事。なぜ自分は満員電車に揺られているのか?って、会社員なら一度は思ったことがあるのではないでしょうか。
思わず読み耽ってしまいました。
著者は会社員生活も長かったようで、我々のような勤め人の悩みを同じように抱えてこられたのだと思います。
どんな本?
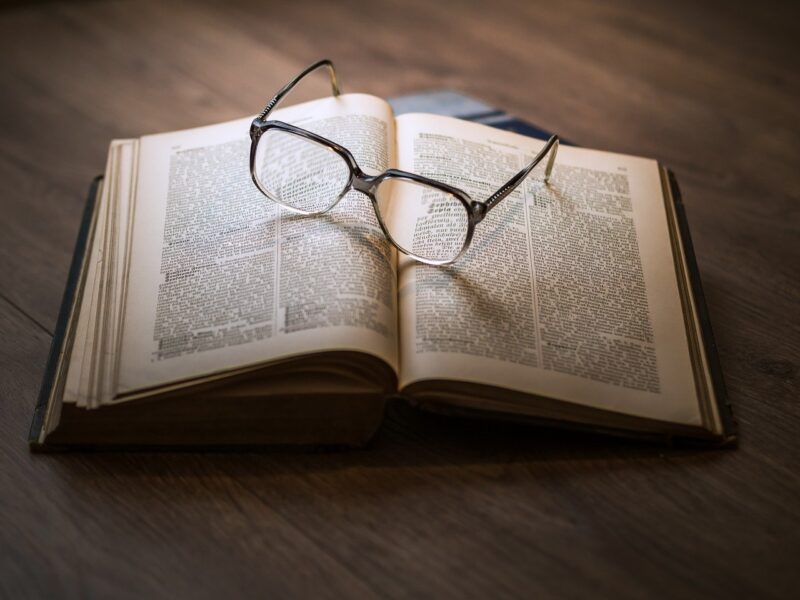
雑誌の特集によくあるノート術や手帳術。
その道(?)の達人たちのようにキレイにまとめるのって難しいですよね。
本書は、きれいなノートの取り方の指南書とは異なります。
とにかく頭の中の考えを全て書き出すことに重きを置いています。
むしろ、自分でも読めないくらいの汚さでもいいから、と。
一人ブレインストーミングといったところでしょうか。
本書では、「ノートを持って、カフェへ行こう!」という帯のキャッチフレーズのとおり、一人で没頭できる場所でひたすら考えをノートに書き出すという「一人合宿」が勧められています。
こういう作業って、特に短時間であれば静かすぎるよりカフェくらいのザワつきがある方がかえって集中できたりしますよね。
この記事の下書きをしている今、深夜ということもあってそこそこ静かだったのですが、やたらうるさいバイクが通り過ぎて行って、意識を持っていかれました。
なんのアピールなんでしょう。うるさいバイク。
誰もいない一時停止線で、「止まった」、「いや、ちょっと動いてた」、なんて争ってないで、こっちを取り締まってほしいです。うるさいバイク。
集中力を保つのって簡単ではありません。
カフェなら、隣で妙なビジネスのお話が始まらない限り、もっと集中できそうな気がします。
一人合宿とは?

著書の中で、カフェで一人こもって作業することを「一人合宿」と命名されていますが、私はこれを、知恵を絞り出し、思考を深めるエクササイズのように理解しました。
頭の中だけで考えるのって、人によって程度の差はあれど、限界があるという気がします。
ノートに書き出すことによって、書き出したものを一旦手放して他のことに意識を向けたり、ぐるっと一回りした頃にそれが目に入ることで新しい視点が生まれたりすることもあるでしょう。

本書では紙に書くことを推奨されていますが、
デジタル派の方は本書のやり方をデジタルで再現しちゃってもいいかもしれませんね。
ノートと筆記具
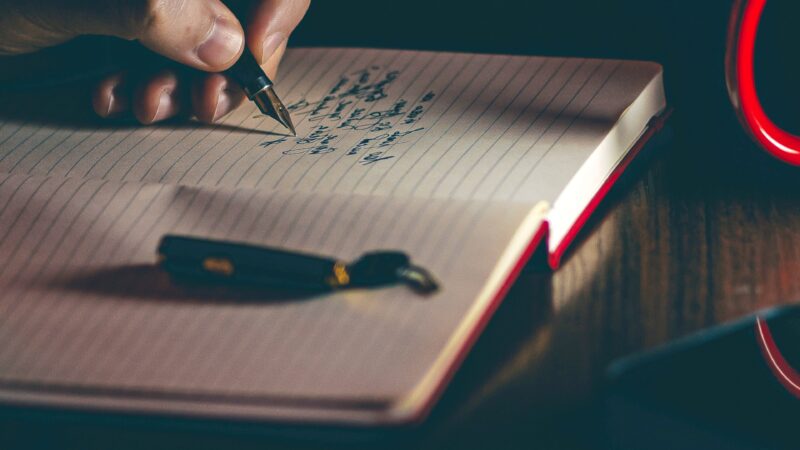
著者では、基本的にノートも筆記具も何でも良いとされています。
- 筆記具は黒一色でよい
- ノートは書きやすく、かつ高すぎないもの
それぞれ気が散らないように、とか、頭の中を吐き出すために「きれいに書かなければ」という発想が邪魔になる、などと、なるほどと思わせてくれる著者の体験が書かれています。
お気に入りの万年筆やボールペンとノートを持ってカフェに行く。
スタバでMacもいいですが、こっちもなかなかダンディではないですか!
管理人オススメの筆記具
万年筆は書く力がほとんど必要なく、長時間の書き物に最適です。
ペリカン スーベレーンは万年筆の代表格。書き味もさることながら、落ち着きのあるデザインで長年の相棒となること間違いなし。
持っているだけでダンディ。
Lamyのボールペン、お手頃なお値段でありかつカッコいい。普段使いに最適です。
持っているだけでオサレ。
本書でオススメされているノート
燕ノートは裏写りもせず、万年筆に合う紙質です。
上質に触れるとはこのことでしょう。
まとめ
- ノートにひたすら頭の中の考えを吐き出すことで、気がついていなかった何かにたどり着けるかも!
- 考えを整理するために、書くことは重要
- 一人合宿は、頭の中でモヤモヤしていた考えを整理する作業であり思考の訓練である
管理人は字があまり上手くありません。
小学校の書初めの宿題は、字が上手くて短気な親父の指導が嫌だった記憶しかありません。
そして管理人は絵も上手くありません。
小学校の写生の構図は、ほぼ全面を水色に塗って「空」と題して提出し、やり直しとなりました。
字も絵も苦手なくせに、筆記具やノートが好き。
そんな人にもうってつけのノート術。
そして本書は、スッと頭に入ってくるシンプルな内容や、適度な文字間隔。
本を読むのはそこそこにして、アウトプットしてみては如何?という著者のメッセージがストレートに伝わってきて、背中を押してもらえると思います。
現状を打開したいと漠然とお考えの方にオススメの一冊です。
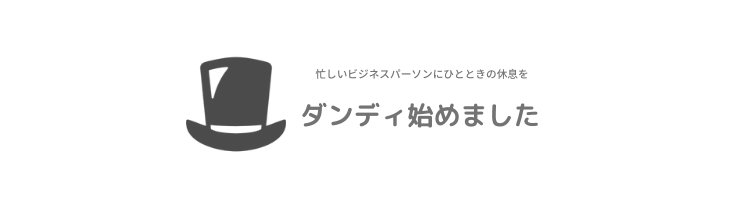




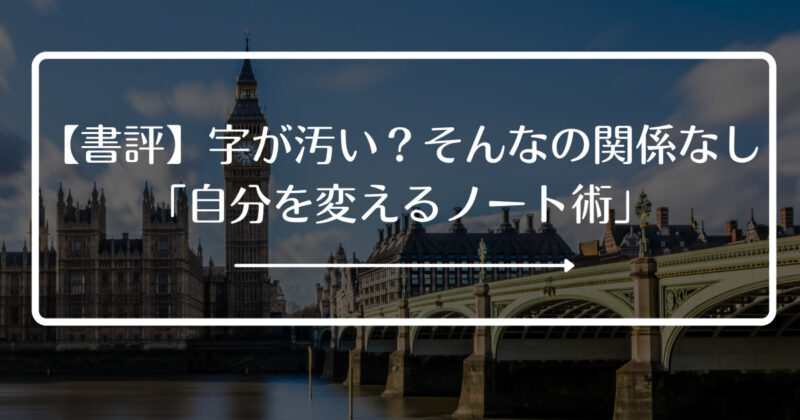


コメント